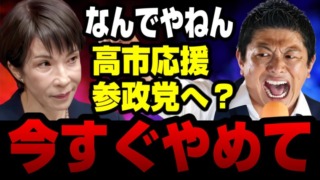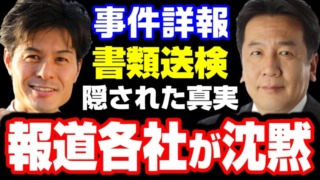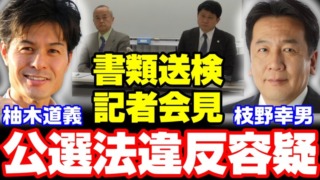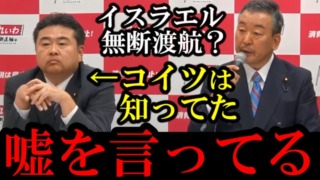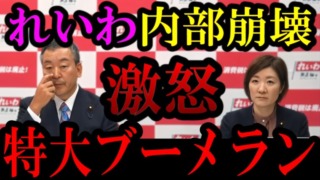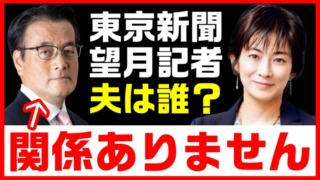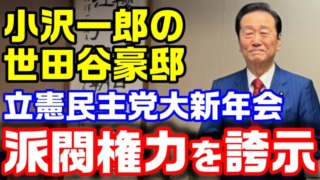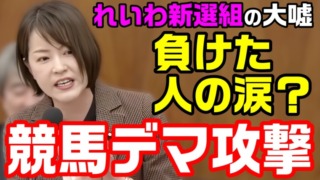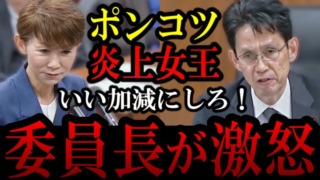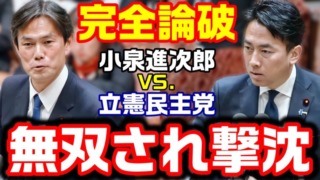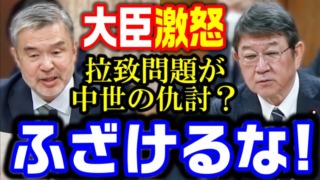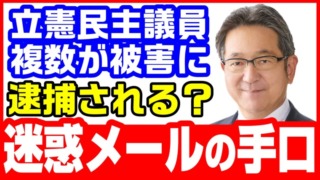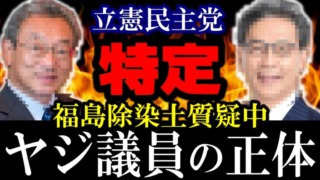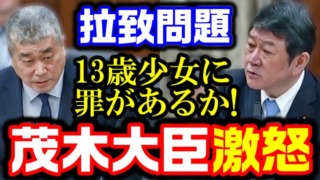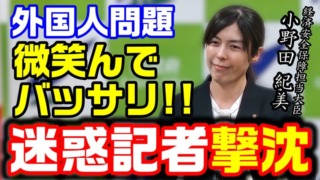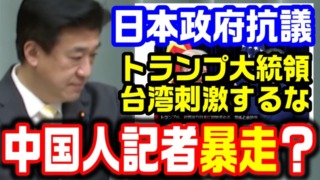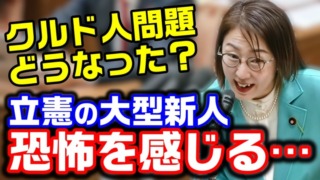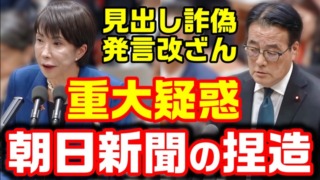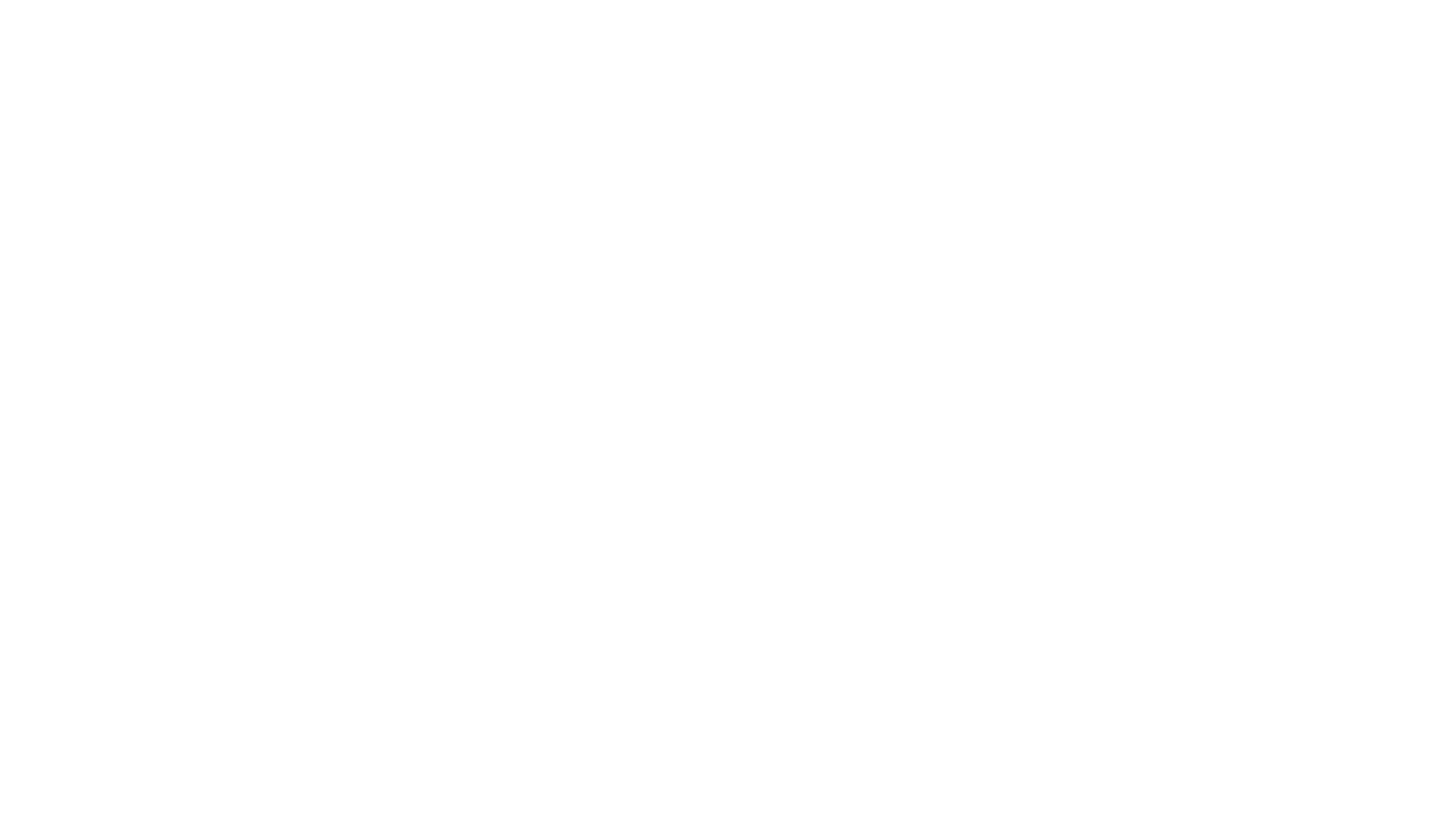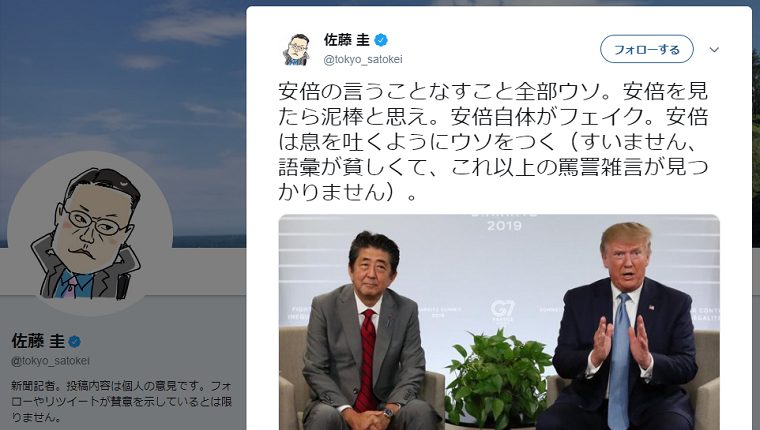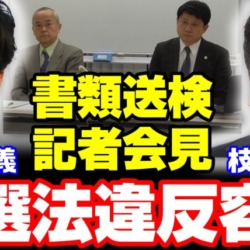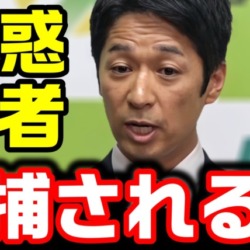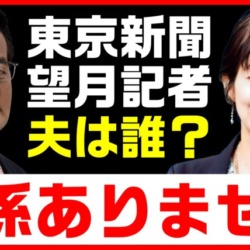【都議選】れいわ新選組が全滅!参政党は躍進!山本太郎の誤算と神谷宗幣の戦略とは?明暗分かれた理由【KSLチャンネル】

22日に投開票が行われた東京都議選で、れいわ新選組の候補者が全員落選しました。これに対して参政党は4名中3名が当選する躍進を見せています。
なぜ、れいわ新撰組は惨敗して参政党は躍進したのか?これは国政と自治体での活動の違いを理解しているかどうかで明暗が分かれています。
国政では、れいわ新選組が勢いを増し14議席を擁していますが、これが自治体議員となると54名しかおらず、対して参政党は国政で4議席しかないのに自治体議員は150名に達しています。
今回の都議選では、れいわ新選組は党の知名度を上げ意気揚々と臨んだわけですが、候補者3名が当選圏内にまったく手の届かない低得票でした。一方の参政党は4名の候補のうち3名が巨大政党の候補者を抑え上位当選、落選した1名は出口調査では当選圏内でしたが、当確ラインに得票率でわずか1%届かず惜敗という結果でした。
両党の考え方に決定的な違いが
自治体選挙での両党の差は、選挙前と当選後の活動内容を見ても明確に差が出ています。
れいわ新選組の自治体議員は党務に集中する傾向にあって、他の自治体選挙の応援や山本太郎のタコ踊り宣伝ばかりで、地元課題への取り組みが全く見えてきません。
一方で参政党は、市議なら普通に市議の仕事をしています。目立つ街宣などでは、いかにも参政党という内容の演説をしていますが、普段の活動では自治体の問題点などについて聞き役となっているわけです。れいわ新選組のように、いきなり消費税がどうのこうのと持論を展開したり、一般人に向かって政府の悪口を言ったりしません。
れいわ新選組は基本的に有権者の不満や不安を煽って、悪いのは自分ではなく政府なんだと洗脳するような言説ばかりですが、これだと一定のそういう他責思考でうまくいってない層から党への支持は得られ国政の比例票を稼げますが、自治体選挙では比例制度がなく候補者個人の資質が有権者の判断材料となるので、いくら山本太郎の知名度を強調して政府の不満を煽ったところで票にはなりません。
自治体選挙では「この街をどうしていくか」ということが重要なのに、消費税ガー!政府ガー!大企業ガー!と国政マターを叫んだところで信用は得られません。
参政党は早い段階で「脱・神谷」を意識して、党員に人気のあるボードメンバーで聴衆を集めたところで、それは組織を奮起させる効果はあるが、新規の党員獲得や選挙での得票に繋がっていないことに気が付いています。神谷代表も以前から、地元活動をしっかりしていないのに「神谷を呼べば勝てる」という甘い考えを厳しく指弾しています。
参政党も選挙に関係無く党の宣伝活動を各地で行ってますが、あくまで「お願い」という姿勢で、一方的に党の話をすることはありません。政策や主張について問題を指摘されることもありますが、そもそも、そういう賛否が分かれる話を無理に持ち出さない穏当な活動が中心です。
これが、れいわ新選組となると「あの山本太郎の」とか「消費税は悪税でぼったくりだ」「全国でのデモで支持を伸ばしている」とか、一方的な自慢話と持論を展開し始めるので宗教勧誘の類としか見られていません。それはそれで他責思考の人たちの支持拡大にはつながっているのでしょうが、地元の方のお困りごとを聞こうという気は微塵もないので自治体選挙では嫌われます。
山本太郎が都議選の最初の週末に石川・長野、最終日には沖縄でのタコ踊りデモを計画して都議選応援を日程に入れてなかったのも致命的で、党勢拡大で慢心があったと言えるでしょう。各党が党首クラスを始め総力戦を展開したのに、山本太郎はデモが中止になればふらっと応援に来るというやり方で、まったくやる気も感じられませんでした。
要するに、れいわ新選組は党への比例票を集める活動が中心で、参政党は候補者個人への票を集める活動が中心なわけです。自治体選挙は比例制度がなく、国政でいう小選挙区・中選挙区のような戦いになるので、党の政策より個人の資質が評価対象となり参政党が圧倒的に強いわけです。